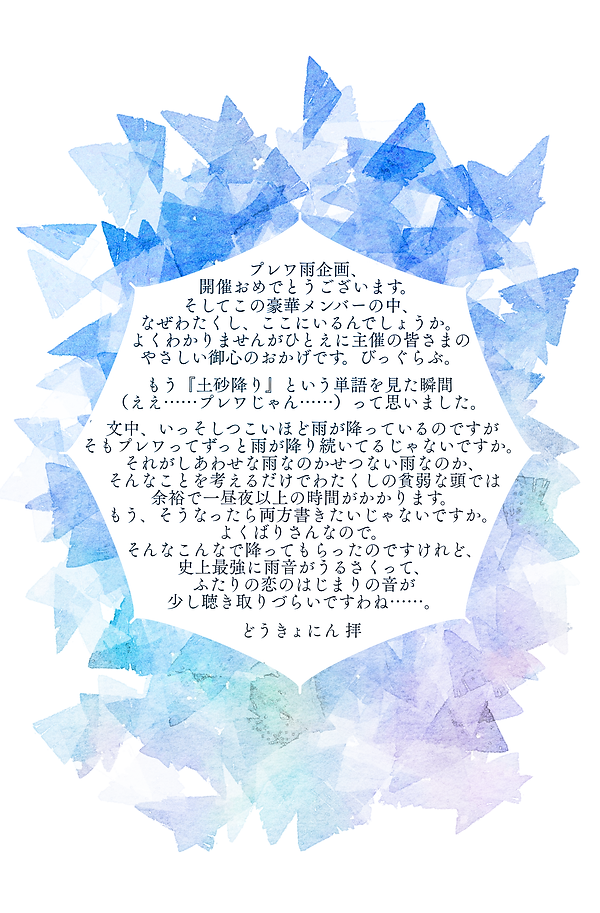ブルーフラワー
どうきょにん
死んでもいいと思った。
あんたが手に入らないことなんて、ずっと前から知っていたのに。
◆
轟音が、耳をかすめていく。
耳に入ることができないほど大きなその音は、からだに強く鞭を打つ。
痛む肌が、声にならない叫びをあげる。声なき声が、こころの中まで反響する。
ほとんどなにも感じることなどできずに、ただ立ちすくんでいた。
しかしからだに打ちつけて砕けた音は、やがてその奥に低く響き始める。
ドラムを叩くように、鉄の扉が閉まるように、腹に刃が刺さるように。
そんな感覚がからだの中を駆けて、そしてようやっと、音が耳を蹂躙する。
自分を翻弄し、振り回し、突き放して、孤独が支配していく。
音の四面楚歌は、あばらを圧迫して、内臓を押しつぶし、筋肉を硬直させる。
しかし次第に、その音に耳が慣れていく。轟音はやがて、しじまにも思えた。
その音へ抱いた感情は、自分が受けた衝撃ときっと同じだった。
それは季節外れの土砂降りだった。頭から打ちつけてくる雨は、そこに立つ者を一瞬間で黙らせる。
打たれるまま、ワードはその道の上でなにもできないままに遠くを見つめていた。
季節にそぐわないほど冷たい雨は、泣き出しそうだった空からこらえきれなくて落ちてくるようにも見える。
鼻先を、水滴が走った。
肌を駆ける雨水は、顎を抜けて、重力に従って下へ下へ、地面めがけて落ちていく。
そうして雫は雨とふたたびあいまみえて、一緒に溶けて混じっていく。かたちもなくさらさらと、そしてどろどろに溶け合っていく。
それらと一緒に混じることもできずに、ワードはじっと正面を、焦点も合わないままに見つめ続けていた。
足元を歩く蟻さえ巣穴に帰るのに、——俺はどこへも行けない。
道は長く続いている。土砂降りの、車も走らないそのひとけのない道で、ワードは立ちすくんでいた。
投げつけられたひとことが、轟音の隙間を縫うようにひとつ、またひとつと刺さった。
はじめは針ほどの痛みだった。取れたボタンを縫うとき、指抜きのない薄皮に針先を当ててしまったような痛み。
いや、痛みもない程度だったのだ。それが串になり、アイスピックになり、包丁になった。
その痛みが次第に全身を刺した。切りつけて、抉って、全身が痛んだ。
痛い。からだを打ちつける雨が痛い。刺してくる言葉のナイフが痛い。
こころが血を噴き出しているのを、ワードは立ちすくんだまま、こらえている。
雨は非情だった。スラックスが鮮やかな黒に変わり、シャツは色を失い肌を透かした。工学部の象徴がついたネクタイはぺっとりと重しになっていく。
縫製を解いてしまいそうな激しい雨は、降り始めたばかりでまだやみそうにもない。
季節外れの土砂降りだったけれど、ゆうべからの天気予報は雨だと教えてくれていて、傘だって持っていたはずなのに、どこかへ——そうどこかへ、思い出したくもないどこかへ、忘れてきてしまった。
うしなった傘のことを頭の隅で考える。透明な傘だった。急に雨に降られたときに手に入れた安い傘、それはわかっている。
少し骨が弱くて、華奢な傘だった。本当にその場しのぎで買ったもの。
——違う。買ってもらったもの。絶対に手放したくないと思って、そのひ弱な傘をずっと大切に使っていた。
この雨はまるで自分のこころを映しているようだと、ワードは思った。
降るのがわかっていたのに、どうしても——これはただの勝手——避けられなくて、やまない衝撃を受け続けている。
世界が色濃く変わってゆく。土煙すらねじ伏せて、かなしみが降り注いでいる。
狂おしいほど焦がれる名前を口にのせたいだけなのに、雨がそれを阻む。
呼吸すらできない。豪雨に、苦しい喉が喘いだ。
まるで底のないプールの中で溺れているよう。
もがいて、口から最後の空気が抜けていっても、それでも天上にあるはずの癒しを求めて手を伸ばす。
でもそこに癒しなどなかった。酸素のない雨の中、くずおれそうになる。
嗚咽が喉をこみ上げた。
空が泣いているのか、自分が泣いているのかもわからなかった。
固まって動かなかった腕が、軋みながら登ってくる。冷えて力の入らない手を、口に押し当ててみる。
雨に濡れた手は、拷問の布のようだった。繊維の間を水が埋めて、空気を与えない。
ぐ、と喉がまた鳴った。
このまま消えてしまいたかった。
雨に溶けて、排水に流れて、きれいに濾過されて、こんな感情などなくして、そして海に流れてしまいたかった。
たとえいちばん聞きたくなかった言葉でも、その口から出た真剣なテノールが自分の最期の記憶になるのなら、構わないと思った。
『ワード、お前は——ノーンだ』
◆
死んでもいいと思った。
きっとあんたがどうしてもほしかった、ただそれだけなのに。
◆
土砂降りの中、意味のなさない傘が近づいてくる。透明な傘が、跳ねる雨に白く見える。
それがあまりに見知った背格好で、今いちばん見たくないひとの顔であることはわかっていた。
ざぶざぶと排水しきれない雨をかき分け、踏みしめてこちらへ向かってくる。
逃げようと思った。——思うのに、からだはいうことをきかない。
靴に浸み込んだ雨が思いがけず足を引き留め、服が、濡れた髪が、からだを凍らせる。
動け。動けよ、早く。
あのひとが来てしまう。
今あのひとを見たら正気じゃいられなくなる。
そう頭では必死に考えるけれど、目すら逃げられずに、捕らえられる。
精悍な視線が、火花を飛ばしそうにぶつかる。
「ワード」
そのひとは、俺をまっすぐ見ていた。
男のまわりだけ、雨が降っていないようにすら見える。
ピープレーム。たったひとり、ずっと焦がれて、ほしくて、ほしくてほしくてたまらなかった男。
「お前、雨降んのわかってたくせに——傘、置いていくなよ」
差した傘を少し持ち上げて、主張する。
それはひ弱な傘だった。まるで今の俺みたいに、豪雨に打たれて軋んでいる。
「ワード」
返事が思い浮かばなかった。
なんですか。追いかけてこないでくださいよ。いいじゃないですか、雨に濡れてみたい気分なんです。
そんなあてつけのような、阿呆みたいな答えでもよかったのに、口は動かなかった。
「なんだよお前、——らしくねえぞ」
らしくなくさせたのは、あんただ。
そんな文句のひとつも言えたらいいと思うのに、もうなんにも考えられなくなって、あんたの顔ばかり見てしまう。
心配する表情が眼前いっぱいに広がっていて、どうしても目をそらせない。
「……ワード」
あんたになんて言われても、俺はあんたから目が離せない。あんたしか今、目に入ってこない。
◆
死んでもいいと思った。
あんた以上に好きになれるひとなんて、きっと見つからない、だから。
◆
「ワード」
先輩が俺を揺する。傘が頭の上で揺れて、雨がさえぎられる。ぼたぼた、と傘の爪からこぼれた大粒のしずくが肩を刺激する。
「なあって」
「……なんなんですか」
自分の口から震えるように出たその苛ついた声は、傘の中、なににもさえぎられずに男の耳に届いたようだった。
「なんで来たんですか」
「なんでって」
「来なきゃいいじゃないですか」
呼びかけをやめた先輩は、またじっと俺を見ている。俺もじっと、先輩を見ていた。
さえぎるものなどなにもない。視界に入るのは先輩と傘の鈍色の細い柄だけで、なにもないのに。
——あんたが今、世界でいちばん遠い。
届かない宇宙の向こうに手を伸ばすような気持ちで、その黒い瞳を見ている。
「あんたは俺のことただのノーンだって言った。それが全部でしょ」
自分で言った言葉が、俺の奥深くを握りつぶした。痛みが、今の俺を生に引き戻す。
「ただのとは言ってねえだろ」
「言ったのと変わんないですよ」
呼吸を止めたい。止めたら、この嗚咽をあんたに聞かせなくて済むのに。
「……なさけない」
俺は親指で鼻をこすった。吸って、ず、と低い音を立てる。
「こんな、こんな——つもりじゃなかった」
は、と詰めていた息を吐く。まるで泣いているみたいで、いやになる。
「あんたなんか好きになるつもりじゃなかった」
雨音がうるさい。さっきまで聞こえなかったのに、先輩が傘なんか持ってくるから一層耳に入るようになってしまった。
「なんであんたのこと、好きになったのかわからないんだ」
傘の中から出て行けずに何度も反響する低い水の音が、顔に、髪に、肩にぶつかる。
「いつの間にかあんたのことばっかり考えてる。あんたが前を通ったら背中ばっかり目で追いかけるし、あんたの声が聞こえたらずっと聴き耳立ててる」
雨が降っていた。そのしずくは、俺の目の奥の積乱雲からもとめどなく降り注いでいる。
「こんなに好きなんだ。どうしても、あんたがほしい」
時空をゆがめて、この土砂降りの雨を降る前に戻して、あんたに告白なんかしない時間まで巻き戻して、ただのノーンのままに戻りたい。
俺の中のあんたを、いちばんなんでも話せる、頼れる憧れの先輩に戻したい。
あんたのことが好きになる前の俺に戻りたい。
得体の知れないこの感情をなくしたい。
なのにもう、あんたのただのノーンには戻れない。ただのピープレームに戻すこともできない。
土砂降りの雨は傘にさえぎられて、こころごと水に流してしまうこともできない。
もう戻れないところまで来てしまった。
どこへも帰れないところまで来てしまった。
「嫌いになれたらよかった」
◆
死んでもいいと思った。
俺の存在が傷になって、あんたのなかに一生残るなら。
◆
それはべつに、決死の告白ではなかった。
ただ思わず口から突いて出てしまって、引っ込めることができなくなった、ただそれだけの話だった。
曇り空、いつの間にか友人になった仲間うちで昼飯を食べながら——それこそオークの入学後通算八回目のナンパ失敗談を笑いながら——喋っていた。
『九回目も同じ轍を踏まないことを祈るよ』
コングポップがそう返し、水を飲む。
『ていうかオークはどうして懲りないの?』
エムは純粋な疑問でオークを刺す。
『でも面白いからもっと聞きたいな』
ティウはサディスティックに笑う。
満身創痍のオークは、藁にも縋る思いでこちらを振り向いた。
『ワードは俺のこと、もっと優しくいたわってくれるよな……?』
きゅるんとした顔で俺を覗き込むオークは、お願い優しくしてとその大ぶりのレンズの奥から俺を見つめる。
『馬鹿につける薬なら切らしてる』
『薬なんかいらないからかわいい彼女がほしいんだってば』
机に突っ伏したオークを四人同じ顔で見やり、そして同じ顔でお互いを見つめ、同じように肩をすくめる。
これから次の講義までの空き時間で、メイたちも混ざって課題のレポートをする話になっている。
昨日いっそ華麗なほど惨敗したらしいオークはきっとなにも手につかないだろうね。コングポップは片眉を上げ、目線でそう訴える。
伏せたオークの向こうに、鳥が飛んでいた。帰宅を急ぐ、名前も知らないあの鳥は、きっとこれから雨が降ることを知っていたはずだった。
『おう、お前ら楽しそうだな。混ざっていいか?』
エムの肩をぽんと叩いたのは、タイのチャラ男代表——ブライト先輩だった。
『楽しそうか? 昼飯のどに詰まらせて死んでるやつがいるぞ』
生きてるか、まだパッタイ半分残ってるぞ。オークの背中をさすりながらノット先輩がからかう。
ぞろぞろと少し前までは異様な威厳を放っていた先輩が寄ってきて、哀れな後輩をいたぶる。
『せんぱあい……女の子がほしいんです……』
『なんだ、女の話かよ。あのなあ、ほしいとか言ってるうちは来ないぞ、押してだめなら引くんだ』
『引いたら出会いがなくなります……』
まったく参考にならないアドバイスにとどめを刺されたオークは、それ以降口を閉ざした。さながら死体だ。
各々好きなように腰掛ける。そんな中、アーティット先輩はぐるりと遠回りしてあえて俺の隣に座った。コングポップから一番遠い席なのは、思いきり意識していることを暗に語っている。
『いいんですか、ここで』
『俺が隣で悪かったな』
『悪いのは俺じゃなくてコングですよ』
目で対角線を見るが、なにをそんなにご機嫌なのか、向こうはにっこりと微笑んでいる。
『いい。あいつの隣に行ったらなにされるかわからん』
アーティット先輩はほとほと懲りたように頭をかいた。オークが見たら泣き面に蜂で即死するだろう。
そしてプレーム先輩はエムとティウの間へ割り込んだ。くしくもそこは、俺の真正面だった。
通算八回目の経緯を愉快そうに聞き終えたプレーム先輩は、じゃあお前らはどうなんだよ、とそれぞれノーンへ目配せる。
『ワードも浮いた話ねえのかよ。——ああスンスンホクソン、お前には訊いてないぞ』
『話そうとも思ってませんよ』
その台詞に睨みをきかせたアーティット先輩に、スンスンホクソンはウインクする。気障な奴。ふたりがカミングアウトしたのはつい数か月の話で、以来、隙あらばコングポップは先輩のもとへ走るようになった。アーティット先輩のほうは毎度駄犬を蹴散らそうと必死だ。
俺もそうなれたら——そんなささやかで、無理なことを考える。
『俺ですか』
対角線上でふたりの世界を築き始めそうなカップルを横目にしてから、えーと、と目を泳がせる。
期待をもって覗き込むプレーム先輩が、言えよ、と顎をしゃくる。——はぐらかそうとして、適当に答える。
『ないですよ。そんな浮かれぽんちになる予定ないです』
『いやあ、そんなことないだろ。誰かいないのか、気になるかわいい女の子とか』
『ひとの弱みを握ろうと必死だね、プレーム』
トゥッタ先輩はコーヒーを飲みながらにやにやと笑んでいる。
『ちげえよ。お前らも知りたいだろ、ワードの普通の男の子みたいな話』
『気色悪……』
『ワードお前、気色悪いとか言うな』
仕返しのように、先輩は俺のサンドイッチをひと切れ奪ってかぶりつく。
『あっ俺の昼飯! 先輩こどもですか!』
がた、と勢いで立ち上がる。周囲からは始まったぞと言わんばかりの好奇の視線が集まる。
『ああこどもだね、俺は知りたがりだからな。教えてくれないなら残りも食っちまうぞ』
『後輩の飯にたかるとか最低』
『言ってろ、今に食い切ってやるから』
むしゃむしゃとうまそうに——そのたまごサンドが食いたくてサンドイッチにしたのに、ケーキのいちごを盗むようなことをして——食う先輩は、じっと上目遣いに俺を見ている。
『あんたが先に言え』
『俺ァ言わねえよ』
なあ、と先輩はノット先輩のほうを見やる。トゥッタ先輩は井戸端会議中のマダムのように口を押さえているし、ブライト先輩に至ってはバラエティでも見るようににやにやしている。
ノット先輩は勘弁しろと言いたげに口を開いた。
『俺に振るな、プレーム』
な、ワード。俺じゃないよなあ。先輩こそ俺に振らないでくれ。
『プレーム先輩が言わないなら俺も言う筋合いありませんよ』
『じゃあお前が言ったら教えてやるよ』
したり顔でにやつきながら先輩が言う。
『好きな奴ぐらいいるだろ、いないにしても今までにはいたろ? 言え言え』
……久しぶりに話せたと思ったのに、こんな話題でこんな態度——。
先輩と呼ぶにはあまりにもらしからぬ行為に、だんだん腹が立ってくる。怒鳴り散らすわけでないにせよ、まるで嫌いだったときの身勝手な先輩のようで、こちらも同じように時を戻してしまう。
『あんたには一生言わない』
『そんなこと言ってっと残りも食っちまうぞ』
『この……!』
コングポップがいさめようと立ち上がったのが見えて、また腹が立った。
俺かよ。俺が悪いのかよ。話を持ち出してあまつさえ飯を奪ったのはこのピープレームだぞ。
正面でたまごサンドに舌鼓を打っている先輩をねめつける。
あんたにこんなことを訊かれるのはいやだ。俺がひっそりだいじにしているものなのに、よりによってあんたがこんなこと訊くのか。俺はあんたがひとの飯勝手に盗むような馬鹿で、ひとの秘密を暴こうとするような最低な先輩でも、いつか助けてくれたやさしいあんたが好きなのに。
あんたが、あんたのことが好きなのに!
『あんただよ!』
言ってしまって、周りがしんとしたのがわかった。
数拍遅れて、しまった、そう思ったけれど、もうみんなの耳に入った言葉は戻ってこないことを悟る。
まずいと頭では考えるのに、からだは言うことを聞かず固まったまま、動けない。
冗談ですよ、なんて適当にはぐらかすことだってできたのに。
『あんたがすきだ……』
かすれて声にならないささやきが、また口をついた。口ばかりが先を走って、からだとこころがついてこない。
置き去りになった感情がすべてを理解するのに、三秒にも百年にも感じる時間が過ぎていく気がした。
時が止まる。でも時間は止まらない。ああメイたちとの約束の時間までもうあとどのくらいだろう。
プレーム先輩もサンドイッチを口に残したまま、じっと俺を見つめている。
ぴい、と鳥が遠くで鳴いた。それが雨の合図だと、俺はわかっていた。
トロクスラー効果が、徐々に先輩以外を消していく。少しでも目を動かせば世界が戻ってきてしまうことを知りながら、戻れずにいる。
先輩、なんとか言って。適当にはぐらかして、気付かなかったふりをして。そう思うのに、先輩は真正面から俺を——俺の感情をあまりにあっさりと殺した。
『ワード、お前は——ノーンだ』
がた、とベンチが揺れたのが聞こえた。自分が背のないベンチをまたいで出た音だということに、あとから気付いた。
背中に、自分の名前がいくつかの声で呼ばれたのがわかった。でももう振り返ることはできなかった。
走るさなか、自分の顔に空からのしずくが当たった。それが鳥の教えてくれた雨で、先輩の答えだということなど、理解したくもなかった。
◆
死んでもいいと思った。
このままひと思いに殺してくれるのが、あんたなら。
◆
「ワード」
先輩が俺の肩を掴んだ。掴まれて、その手の熱さに辟易して、————震える。
この熱に、ずっと侵されてきた。
「もうやめてください。——戻りますから」
その手に手を重ねた。剥がそうとして、まあまあ、と先輩はそれを押しとどめる。
「その前にちょっと話聞いていけよ」
「嫌です。ていうか無理です」
「そう言うなって」
掴んだその手のちからが強くなる。指の肉が俺の肩関節に深く食い込んで、——そして弱まった。
「お前、——冷えすぎだぞ」
まるで今気がついたようなその物言いに、思いがけず苦笑する。
ふにゃ、と。あるいはくしゃっと、自分の顔がやわらいだのがわかった。
「今さらですか」
その様子を見て、先輩もようやっと表情をゆるめた。
「……今さらで悪かったな」
はあ、とひとつため息をついた。それは先輩の口から出たもので、妙なニュアンスを含んでいた。
抱き寄せられたことに、全身をぬくもりが包んだことに、またしても気付くのが遅れた。言葉が出なくなる。
「ワード」
耳元に、先輩のテノールが響いた。
猫に問いかけるようにやさしい声が、水の中に一滴酒をこぼしたように広がっていく。
慣れないアルコールが、からだを火照らせる。
「……っ離せ」
「ワード」
「離せ!」
暴れても、先輩のからだはびくともしない。
傘がころんと自分の背後に落ちたのがわかった。
雨が降り注いできて、先輩の乾いた首筋が、みるみる結露するように濡れていく。
濡れるから。あんたのシャツも、髪も、濡れるから離して。
やさしくするな。
なのにおとこのひとのちからは、どうしてこんなに強い。
「——離せよ……」
泣きごとのようにわめく自分の声を届けようと思うのに、先輩は聞き入れてくれない。
「ノーンだよ」
抱きしめるのと同じくらい強いその言葉が、また俺を突き刺した。
「お前は一生ノーンだ」
重なる耳が、お互いの声を聴いている。
あんたのその言葉は、俺をどうにでもしてしまうのに。
「わかってます。もう聞いた」
「わかってないのはお前だ」
「わかってる! だからもう」
言わないで。先輩のシャツを握りしめた。突き放したいのに、——ちからがうまく入らない。
あんたにどれだけ傷つけられても、どれだけ壊されても、あんたを突き飛ばすことができない。
「お前はノーンだからなあ」
その少し間抜けなほどの語尾が、俺の耳に引っかかった。
「……なに」
その変な言い方。首を先輩のほうへ向けると、先輩も同じようにしてこちらを見ていた。
すぐ目の前に、先輩のころんとした鼻があった。そのすぐ上に、八の字の眉と垂れ目がちょんと乗っかっている。
「お前がノーンだって言い聞かせてきたからなあ、俺」
「は?」
「いや、そりゃアーティットとコングポップはああだけど、あれだけ俺らを毛嫌いしてたお前がそう思ってたとは思わなくてなあ」
しみじみしたように言葉を続ける先輩が、さっきまで真剣な顔して俺の名前を呼び続けた先輩とは別人のようで、どこか拍子抜けする。
「お前、まだ上に対して妙な壁があるだろ」
ばれてないと思ったか、先輩は口角を片方だけ上げる。
「一時期よりは丸くなったけどな。大学入る前になにがあったか知らんが、お前、先輩っていう立場の人間に対してなんか距離があるんだよ」
目上のみんなに対してそうだぞ、そう諭す視線が痛い。
「多分今は、お前も気付かないところで壁作ってるんだろうな。言葉というより、仕草というか……雰囲気に出てる」
出てるんだぞ、と額をぶつけられる。近い距離がゼロ距離になって、まばたきすらはばかる。
「そんなんだからまさかお前が俺を好きだとはなあ」
「……馬鹿にしてんですか」
「違う」
重なった額をぐいぐい押される。鼻先が、くちびるまでもくっつきそうで、——きっとわかりやすいほど、動揺している。
「だいいちお前、言葉の表面ばかり捉えすぎだ。ちゃんと続きを聞け、続きを」
つづき。言葉尻を拾う鳥のような俺の言葉に、そうだと先輩は言う。
「お前はノーンだ。で、俺はピーだ。あくまでもな。だから今まで……いや、そもそも言うつもりはなかったけど」
一分前までなによりも聞きたくなかったはずのその言葉の先を、じっと、俺は待っていた。
「俺もお前が好きだよ」
雨の音が、また聞こえなくなった。
まるで野獣の大事にしたばらのショウケースをかたどるように、俺を、そして先輩をよけて降っているようだった。
「お前をなんとかして諦められないかと思って、根掘り葉掘り訊いたってのに」
先輩の重みが、少しずつのしかかる。
「……なんで」
かすれた声は、雨に邪魔されることなく先輩に届いたようだった。
「いつから」
「知らん。お前は憶えてんのか、いつからとか」
「…………お、憶えてない」
これは嘘だった。嘘でもつかなければ、——勝手な口が、もうなんでもかんでも話してしまいそうで。
「な、そんなもんだ。——で、どうする」
「……なにがですか」
「戻るか。それとも帰るか。風邪ひくぞお前」
シャワーを浴びたようにびしょ濡れの俺の髪を、先輩が前からかき上げた。こそばゆくて、思わず目を閉じる。
「……戻る。かばんも全部置いてきたから」
指が後頭部まで駆け抜けたのを待って、目を開けた。まつげが濡れたその先の視界には、先輩の顔がうっすらぼやけて、そしてきらめいて見えた。
「そうか。……そうだな、俺がやった傘も置いていったもんな」
先輩はそばに転がったままだったそれを拾い上げた。内側に雨が溜まって、それはコップをひっくり返すようにしてこぼれた。
「先輩、……覚えて」
「覚えてるよ、今でも使ってるなんて知らなかったけどな。あのとき、財布に金なくていちばん安い傘買ったんだよなあ」
ものだいじにするのうまいな、俺なら一週間で骨折るわ。先輩があっけらかんと笑うのに、俺はまた文句をつけそうになる。
あんたに買ってもらった、たったひとつのものなのに、そんな粗末にはできない。
傘がまた頭上に来た。返してくれるのかと思ったら、先輩は手に持ったまま歩こうとする。
待って、と思うより先に、足が勝手に先輩を追いかけた。止まった時間が動き出したように、からだはどこかあたたかい。
「じゃあお前、今からこころの準備しとけよ」
おもむろに先輩は口を開いた。脈絡のないその台詞に、横顔を振り返る。
「は?」
「みんな知ってるからな」
——その言葉の意味を理解するのに、また数秒かかった。
「帰ったら冷やかされるぞ。今頃ブライトあたりが全部ぶっちゃけてるだろうからな」
覚悟しとけ、先輩が笑う。
「お前は知らないだろうけど、俺たち、わりとなんでも腹割って話すからな」
傘を持つその腕に、手を絡めてみたい。
先輩に文句をつけながら戻る道すがら、不意に考えた。
絶対に触れられないと思っていたそれが、思いがけずそばに来て、ものの数分でこれだ。欲深い自分の業を思い知る。
狭い傘の中、歩くリズムが重なったときにだけぶつかるその肩に、自分の肩があたるだけで満足していたいのに、——ああ、こんなに好きだ。
こんなに好きなんだ。きっとまだ、あんたは知らない。
いつか虹は出るだろうか。
まだ土砂降りの雨はやまない。
道は、長く続いている。
◆
死んでもいいと思った。
でももう少し、あんたのことが知りたいんだ————ねえ、これを奇跡と呼ばずして、なんと呼ぶの。