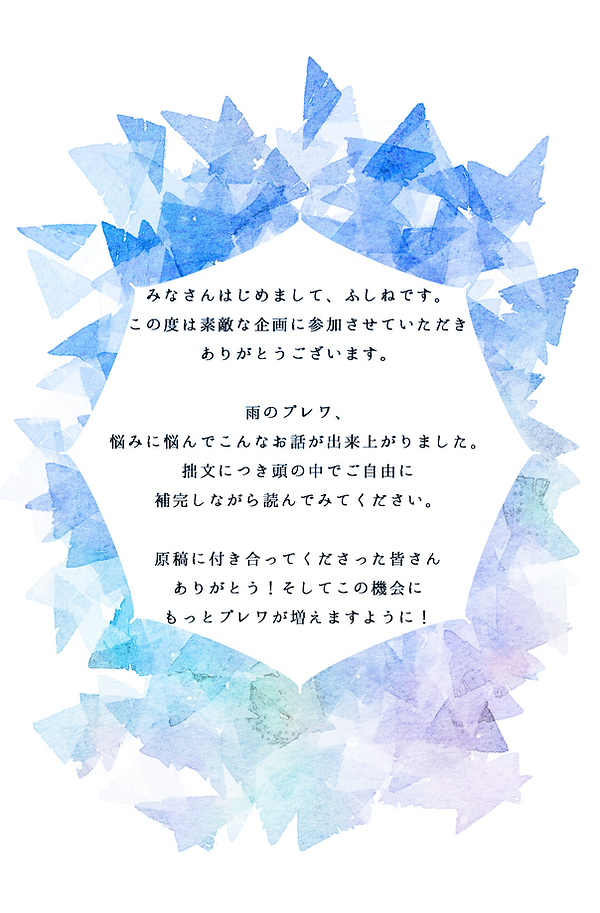雲間の月、カーテンの中
ふしね
月を眺めるのが好きだ。燦然と輝く星たちを率い静謐な夜を際立たせるそれは、見上げているとなんとなく出会った頃のあの人への想望を思い返させる。
名月だという今夜、一緒に月の写真を撮りに行こうという約束は降り注ぐ雨のせいで果たせなかった。
部屋の中からでも良いから一緒に月が見たい。少しの間でもこの雲が晴れやしないだろうか。期待を込めて窓の外を見つめてみるけれど降る雨の勢いは一向に弱まる気配を見せず、外に見える光は雨粒に滲みながら道端を照らすナトリウム灯の、ぼんやりしたオレンジ色だけだった。
「ほらお前も食えよ、これ。せっかくもらってきたんだから」
そう言うプレーム先輩は、なんでもないような顔で月餅を頬張る。
「甘いじゃんそれ」
甘いものは得意ではない。それは先輩だって同じ筈なのに。
「…やっぱり甘いわ、これ」
ほら、やっぱり。急に眉を寄せ真顔になった先輩に呆れながらコーヒーの入ったカップを手渡してやる。
「これに浸したらお前でも月餅食べられるんじゃないか?ベトナムコーヒーみたいな味になるかも」
閃いたとばかりにこちらに提案してくる先輩を無視して自分の分もコーヒーを淹れようとしていると「試してみろよ、ほら」と掠めるように唇が重ねられた。差し入れられた舌からはコーヒーの苦味なんてほとんど感じずただただ甘ったるい。ベトナムコーヒーには似ても似つかないその味に思わず顔を顰めると、先輩は笑いながらテーブルの上のタバコを手に取り、ベランダの方へ歩き出した。雨は、まだ止んでいない。
「まだ降ってるよ」
ベランダを名乗るだけあって一応付いている屋根はこの雨を防ぐには些か不十分で、きっと濡れてしまうだろう。気を遣って声を掛けてみたけれど、先輩はひらりと手を上げただけで歩みを止めようとはしなかった。窓ガラス越しに先輩の広い背中を見つめる。反射のせいで表情はよく見えないけれど、その頭の角度から空を見上げているのはわかる。
普段はタバコなんてすぐに吸い終わるくせに今日に限ってゆっくり味わっているようで、その火とフィルターまでの距離はなかなか縮まらない。
ようやく戻ってきた先輩は案の定そこそこ濡れていて、時折頭から滴が落ちる。タオルを被せてやると甘えるように頭を下げ、拭いてくれと強請られた。子供のようなその仕草に悪い気はしない。求められるがままにその水気を拭ってやると、満足げな顔が頷く。
「コーヒー、もっと飲むか?淹れてやるよ」
その言葉に耳を疑う。コーヒーを淹れるのはいつも俺で、この人はそれを飲むだけだった。どんな気まぐれなのだろうか、その真意を読むことができなくてただ渡されるがままに先輩の淹れたコーヒーを受け取った。
窓の外と同じ暗い色をしたそれは普段と変わらないもののはずなのに、先輩が淹れてくれたというだけで特別なように感じてしまう。自分はこんなにも単純だっただろうか。
タバコを吸っていた時の誰かさんに負けないくらいゆっくりと、少しずつコーヒーを流し込んでいく。滲みるような苦味が心地良い。カップの中身を全て飲み干す頃、いつの間にか隣に立っていた先輩の手が肩に触れた。
「ワード、こっち」
手に力が入り、少し離れていた距離を縮められる。慎重なその手つきはやっぱり先輩らしくない。
「なんか先輩、おかしいよ」
眉を寄せて問うてみると、先輩はゆっくりとその口を開いた。
「お前、月好きだろ。…いつもあんまり熱心に見つめるから、名月なんて眺めた日にはあれに連れ去られるんじゃないかって思ってた」
だから今日雨が降って正直ほっとしてる。少しだけ苦い表情で笑う先輩は気恥ずかしく感じているのか、俺の頭をくしゃくしゃに撫で回してくる。
何をすれば引き止められるかわからないのだと先輩は仄めかした。ばかだな。
「…あんたがここにいるなら、俺も一緒にここにいるよ」
他のなにものだって、あなたには勝てないのにね。
部屋の明かりを消して、真っ暗な中何をするでもなくソファに二人寄り添った。閉じた目蓋の上を優しい指先が撫でていく。
このひとは太陽のように全てを明るく照らしてはくれない。けれど何も見えない中手を差し出してくれた。だからあなたは、俺の月。
◇
雨の夜は、月も見えない。
それが俺には好都合だった。
ワードはよく月を眺めている。ベランダでタバコを吸う時、夜の散歩をする時、眠る前。それは、俺と見つめ合う時間よりも月を眺める時間の方が長いのではないかと感じるほどで、こうもあればかり見つめられるとさすがに月のことが嫌いになりそうだった。
月の写真を撮りに行くのだって、正直誘いたくなかった。名月なんて、あいつを連れ去ってしまいそうでおそろしい。それでも誘ったのは、ベタだけれどあいつの喜ぶ顔が見たかったから。
だから、雨が降った時はありがたいと思った。だって、今晩ワードはいなくならない。
眠りに落ちたらしく遠慮なく寄りかかってくる重みを抱え、ソファから立ち上がる。目蓋を伏せ、薄く唇の開いた俺のいとしいノーンは、どこか幼げで愛らしかった。腕の中のこいつを起こさないようにゆっくりと窓際へ向かう。相変わらず雨は降り続いていて、月の光は一筋もこちらへ届かない。
まだ起きる様子のないそれをそっとベッドに降ろし、傍に跪くように座り込んだ。
こいつは一緒にいると言った。それが本心からの言葉なのはわかっている。
それでも自由なお前はいつか些細なきっかけでここを去ってしまうのではないかと不安で仕方がない。その時残った面影に囚われるのは、俺。
「お前のことは、離してやれないよ」
口にしてみると、存外重たく鈍いその言葉にぞっとする。これほどまでに持て余すようなきわどい感情が自分の中にあるなんて思ってもみなかった。そんな燻りを逃してやろうと、目前の足先に唇で触れる。作り物かと見紛うほどに滑らかで冷たい足先はぴくりと震え、その持ち主がきちんと生きた人間であると主張していた。
健康的な肌色。長く伸びた睫毛が縁取る目蓋。凛々しさを称えた眉。こいつに出会うまで愛しさを感じる要素などなかった、整ったつくりの男の顔。規則正しく紡がれる呼吸さえなければ無遠慮に触れてしまっていただろう。
本当はあのナトリウム灯の光さえ邪魔だ。明るいところにいたら、きっとお前は俺以外の誰かの瞳に映り込んでしまう。頼むから、他の何にも見つからないまま、ずっと俺のことだけ見つめていてくれ。
雨はいつの間にか止んでいる。変わらず安らかな寝顔を一瞥して、雲間に顔を出した月からワードの姿を隠すため勢い良くカーテンを引いた。